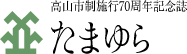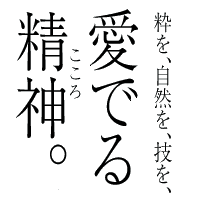慈しみの心を味わう[食]
飛騨では春の祭りが桜前線に沿うように里から山合いの町へと順を追って執り行われ、秋の祭りは紅葉前線に合わせて移動する。
祭りになると家々では呼び引きが行われ、招かれた人々は家ごとに伝わる料理でもてなしを受ける。ふきのとうやなつめ、こも豆腐にぜんまい。どの料理も飛騨の人にとってはお馴染みのものだが、家人の味付けを楽しみながら、訪れる季節を舌で堪能する。
山林が九十%以上を占める高山ではかつて豊かな食材は望めなかった。だから、人々はお正月や祭りなどのハレの日を待ち焦がれ、その日が近づくと普段は口にできない食材を腕によりをかけ料理する。食材を大切に、そして美味しく食べる知恵はこうして生まれ、現代に引き継がれる。
ところで飛騨の人たちの馴染み深い食材といえば山菜だが、春の姫竹(ひめたけ)、秋の茸(こけ)が両横綱といわれる。おいしいことはもちろん、簡単に採れる場所に育たないことも大きな理由で、生息する場所は家人にも教えないという。その理由は翌年も収穫するために足る分だけを摘んでいくという思いがあるからだ。
姫竹は春の山菜が終わる頃に芽吹く。主婦たちは山に残る雪渓を遠くに見ながら『あじか』と呼ばれるカゴをぶらさげ山に入る。採った姫竹は皮をむき、茹でてから塩水とともに瓶に詰め、保存食にする。それによって奥深い味と歯触りは翌年の春まで楽しむことができる。
黒々とした大地と高地特有の気象、さらに作る人の丹精込めた営みによって生まれる「飛騨ブランド」。高山の食の原点はまさしく風土から生れたフードである。
![]()
| < 熟成された時の産物[祭] | 愛でる精神トップ > |
![]()