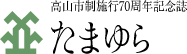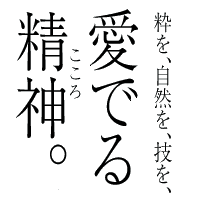業と粋の血脈[工芸]
大胆な造形と、彫刻の繊細さが見事に調和した根付は江戸時代の匠、松田亮長(すけなが)の作と伝えられる。
根付は桃山時代に生まれ、裕福で粋な町衆を中心に愛用された。江戸時代になると、まさに芸術の域へと昇華していったが、、その代表的な匠が松田亮長と谷口与鹿(よろく)の二人である。彼らの作品は日下部(くさかべ)家の根付コレクションをはじめ、市内の各所で目にすることができるが、根付は実のところ今でも実際に使われている。
春と秋の高山祭。裃で正装した男衆たちは、帯に根付を付けた印籠を下げ、町を練り歩く。先祖代々伝わるもの、自分の好みで誂(あつら)えたもの。個性豊かな匠たちの手による、さまざまな意匠の根付は、男衆の誇りであり、小さくてもこの上なく華やかな自己主張でもある。
律令時代には都の造営に携わっていたことが文献に残されていることから、「飛騨の匠」は千数百年の歴史があるといわれている。当時は木を扱う建築技術者として登用されることが中心だったが、法隆寺金堂の本尊である釈迦三尊像の作者といわれる止利(とり)仏師が飛騨河合の出身であるという説、さらに日光東照宮の「眠り猫」の彫り物で有名な左甚五郎は「飛騨の甚五郎」が訛ったものだという説もあり、匠は幾多の伝説に包まれながら語り継がれている。
都の造営で重用された建築家集団の血筋が一位一刀彫を生み、天領の時代になると江戸文化と融合した屋台やからくりをつくり出す。さらには春慶塗や渋草焼などの陶芸、そして家具やインテリアなど、素材と表現を多様化させながら生き続ける「飛騨の匠」。それは、この地に千年の時を越えて伝わる、手業と粋の血脈といえる。
![]()
| < 愛でる精神トップ | 熟成された時の産物[祭] > |
![]()
松田亮長作の根付(制作は寛政時代)
Netsuke (toggles used to attach pouches to the sash of a kimono) by Sukenaga
Matsuda (made in the Kansei Period)
※写真をクリックすると拡大して表示します。