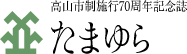にぎわいのあるまち。
にぎわうまちには、さらに人が集まってくる。人と人との交流が新しい活力を生み出していく。
高山には年間、約四百三十万人もの観光客が訪れるが、古い町並みを往来する日本人観光客に混じり、最近では台湾をはじめとしたアジア諸国や、欧州から訪れる外国人とよく出会う。
広重が描いた東海道五十三次や弥次喜多道中から見て取れるように、古くから日本人はこの狭い日本の諸国を旅してきたが、旅はいつの時代も楽しく、面白い。それは外国の人だって同じである。
旅行といっても本格的なアドベンチャーや流浪のひとり旅ではなく、思い立ったら気の合う友人と気軽に行けるような「観光」が主だが、近年では「生産」や「アウトドア」など、観る旅から体験する旅が登場しはじめた。(高山は合併により、北アルプスや奥飛騨温泉郷をはじめ、様々な自然や文化を背景にした個性的な旅の創造が可能になった)
この旅ではくつろぎを得たり、エネルギーが充たされたような感じになったり、物づくりの楽しさを味わったりと、溜まっていた心身の汚れを浄化することができる。さらに、異国の方とこうした時間を共有しながら、言葉の違いや習慣の違いなどを越えて、気持ちを通じあわせるのは得も言われない喜びである。色々な事を考えさせてくれる旅。記憶に深く刻み込まれるのは案外そういう経験なのだ。
![]()
高山市は、最大の資源である地域ブランド「飛騨高山」を活用し、さらなるにぎわいの創出を目指しています。
まず、主力となる観光産業では合併した市内各地の資源を生かし、周遊コースや伝統文化、自然、食など多くのアイテムを提供することで、滞在型・通年型の観光地を確立しようとしています。今後は農業や林業体験を交えたグリーンツーリズムの普及を推進します。
一方で、国内はもちろんアジアを中心とした海外からの観光客の誘致にも積極的に取り組み、併せて市の観光ホームページを一〇言語で表示したり、案内看板を四言語で標記するなど環境整備も進めています。
こうした観光産業の活性化は、人が交流する機会を創出し、消費の拡大を促すとともに、農産物など原材料を供給する産業や関連する周辺のサービス産業への波及も期待され、市民の所得の増加がさらなる消費を生み出すプラスの循環によって経済基盤の安定を目指しています。
現地消費を拡大する観光産業に加え、飛騨牛や飛騨トマト・ホウレンソウなどの農産物、家具産業では飛騨の豊かな自然のイメージとともに「飛騨高山」ブランドが浸透しはじめており、それらの相乗効果によって地域全体のにぎわいから経済活動の活性化へ展開しています。
![]()
| <コミュニケーションのトップ | すみよさのあるまち。> |
写真○ ALT(英語指導助手)を相手に英語で高山陣屋のガイドをする高山市内の小学生
Elementary School Students from Takayama Guiding ALTs (Assistant Language Teacher)
in English at Takayama Jinya (Old Government House)
※写真をクリックすると拡大して表示します。